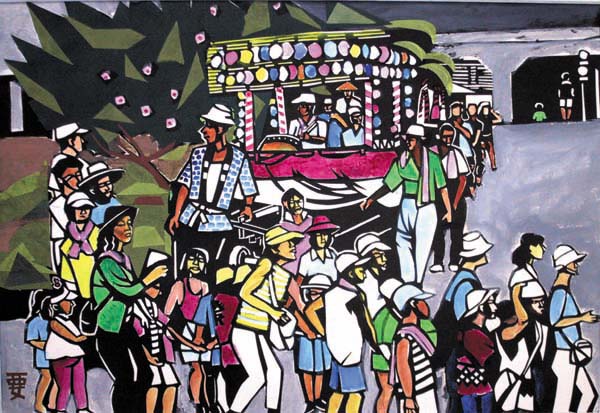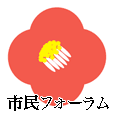日本ワイスレダリーを訪ねて
―日本レダリー(株)は、アメリカン・サイアナミッド・カンパニー(ACC)と武田薬品工業?(株)の出資によって、1953年戦後初の医薬品合弁会社として設立されました。1994年、ACCがアメリカン・ホーム・プロダクツ(AHP/現ワイス)に吸収合併されたことによって、1998年に新会社「日本ワイスレダリー株式会社」が誕生したわけです。
というと、日本でも有名な医薬品会社とアメリカの大手製薬会社の合弁企業というわけですね?
―そうですね。武田薬品の合弁会社のひとつという日本との関わりと、世界の中の医薬品分野でグローバル企業として発展したワイスという会社の、日本における研究、製造、販売拠点のひとつという位置付けです。
では、この志木工場の役割といいますと?
―日本国内で先進的な会社である武田薬品工業、グローバルベースで力をもっているワイス、双方の力を結集して開発された新製品の品質保証をして、日本のお客様にお届けするのが、志木工場の役割です。
主にどんな製品を生産しているのですか?
―志木工場が1963年に建設されて以来、特に抗生物質を中心に生産活動を行ってきました。アクロマイシン、ミノマイシンといった抗生物質は、市民の皆さんには聞きなれない薬品名でしょうが、抗生物質の分野では高く評価されたきた製剤ばかりです。
ただ皆さんが町の薬屋さんで買い求めるような家庭薬ではなく、医療機関から処方される医療用医薬品だから、市民にとってはワイスレダリーの薬のパッケージもなじみがないんですね。現在、生産されている製剤はどんなものが柱になっているのでしょうか。
―現在は、抗生物質、抗がん剤、抗リウマチ剤、婦人科領域の製剤、神経科領域の製剤の、五本の柱を基盤にして製造および輸入、包装を行っています。
抗がん剤というと?
―アイソボリン、メソトレキセートなどが特に有名でしょうが、主に胃がん、大腸がんに作用する薬ですね。
抗がん剤領域でも評価されていますが、特に注力しているのが、抗リウマチ剤です。現在ワイスの生産しているリウマチ薬は、欧米では大変評判がいいのですが、日本ではまだ発売に至っていません。リウマチ薬に関しては、日本は欧米に十年ほど遅れをとっています。トッププライオリティーとして一刻も早く良薬を日本の患者さんに提供すべく、猛スピードで臨床試験を進めているところです。
では、婦人科領域、神経科領域とは、具体的にどんな製剤ですか?
―婦人科領域では、ピルに代表される経口避妊薬や更年期障害、骨粗しょう症などの疾患に対する医薬品ですね。神経科領域では、抗うつ剤の開発に着手しています。従来からある薬とは作用が異なり、ストレス等によるうつ状態を解消させるものですね。そのほか、具体的に製剤名を挙げればキリがありませんが、市民の皆さんにはなじみがなく、「ああ、あの薬ね」というわけにいきませんので、このくらいに……。
ただレベルの高い技術を駆使して、日本国内でも世界的にも医薬の分野で貢献できるよう、鋭意研究開発に努めております。
現在、志木工場には何名くらいの方が働いていますか?
―三五〇名ほどですね。三百名が生産に携わり、五十名が研究所関係です。
時おり、求人もしているようですが。
―製剤の生産量は時期によって違いますから、その際生産活動を協力してもらうために、アルバイトを募集します。生産部門の包装作業がメインの仕事です。
じゃあ、地元の市民もここで働く機会があるかもしれませんね。
―当社は緑と周囲の調和を重視していますし、工場内は大変清潔です。ラジオアイソトープなどの危険な物質は扱っていませんから、安全な職場です。
ただし医薬品を扱っている以上、間違いがあっては困りますので、ルールはかなり厳しいですよ。
企業として、地元の人たちと触れ合う機会はありますか?
―毎年、春と秋に市をあげて行っている川のクリーン作戦の日には、毎回社員とその家族を含め、八十名ほどが参加させてもらっていますよ。
その際、地元の多くの方々とお話しができてとても有意義です。地元の企業として、市民とのコミュニケーションの一環と思って参加しています。
これで御社の概要や姿勢が少しでも市民の皆さんにわかっていただけたかと思います。お忙しいところ、ありがとうございました。今後の活躍をお祈りしております。

|
「バイオテクノロジー」生き物の『バイオ』と『テクノロジー』をつなげたもので、文字通り生き物を使って私たちの生活を豊かにすることが期待されています。
「生分解性プラスティック」プラスティックは、使うときには便利なのに、廃棄するときには厄介なもので、土に埋めても、海に捨てても壊れない、腐らない。
さらにその中に含まれる塩素は燃やすと環境をいちじるしく汚染するものです。 プラスティックは有機化合物、われわれ生物も炭素と水素を主な成分とする有機化合物、考えようによっては同じものなのです。 それなのに土に埋めたとき、生物は土の中の微生物で水と炭酸ガスに分解され、姿を止めなくなり、プラスティックは残ってしまいます 。 そこで従来のプラスティックとは異なり、土の中の微生物が好む(分解できる)プラスティックを作ろう、このような目標に対して多くの基礎研究が積み重ねられ、 ようやく実用的な段階に近づいてきました。 素材はトウモロコシなどのデンプンを原料として作られ、工業的な改良は精力的に進められています。 まだ価格は高いですが、技術的な障害は日々取り除かれつつあります。 「ubiquitous -ユピキタス-」とは「いたるところに存在する」という意味のラテン語です。「どこでもいつでも当り前のように使える」ということです。
総務省は、多くの人が毎日活用できるネットワーク環境の実現に向けて、産・学・官の一層の連携を強めるべきだとする報告書をまとめました。 次世代の製品はユピキタスなもの、という目標に向かって、企業は使いやすい製品の開発にしのぎを削るようになりつつあります。 次世代のパソコンやネットワークはより使いやすいものになることは間違いありません。 |