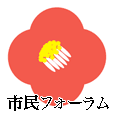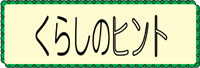
新型肺炎の病原体をもう捉えた
「SARSウイルス」と命名
東南アジアを中心に、多数の死者を出している重症急性呼吸器症候群(SARS)の病原体が、オランダでの感染実験などをもとに、WHO(世界保険機構)により新型の「コロナウイス」と断定された。
患者は中国から香港に、そして航空機の旅客によってアメリカなどにも広がり、世界を震撼(しんかん)させた。WHOが3月にこの疾患に対して警戒警報を出してから一ヶ月余り、未知の病原体がこれほど短期間で確認されたのは、感染症対策の史上、初めてのことだという。
原因が究明されたため、今後ワクチンの開発などの対策が進むはずだ。しかもこのウイルスのゲノムもすべて解読された。塩基数(遺伝子を構成するユニットの数)は二万九千七二七だったという。科学的な研究はいままで考えられなったスピードで進んでいる。高度になったサイエンス、テクノロジーの成果、そして国際的な協同作業の賜物であることを忘れるべきではないだろう。
「ヒトゲノム」が解読された
人のすべての遺伝情報であるヒトゲノム(参考資料例・WEBサイト「NHK・遺伝子―DNA―」http://www.nhk.or.jp/dna/など)の解読企画で、日米英など六カ国首脳は、4月14日「解読完了」を宣言した。遺伝子は約三万二千個とわかった。
人の遺伝情報は人体の設計図で、細胞の核の中にあるDNAに刻まれているのだが、DNAは四種類の塩基(ユニットあるいは文字のようなもの)が鎖状につながっている。今回二十八億六千万の塩基の配列が読み取られ、その精度は 99.99 %以上だという。日本からは理化学研究所や慶応義塾大学などが参加した。
人間の遺伝子をすべて読み取る、というような大逸れたことを考えた人はかつていなかっただろう。手作業ではまさに天文学的であったから。それではいま何が変わったのか。
ワトソン、クリックがDNAの二重らせん構造を解明したのは、1953年のことだった。塩基配列を自動で解析する分析機器の開発、データを処理するコンピュータの進歩と普及によって、この作業は実行可能なところに到達したのだ。日米欧で解読の国際コンソーシアムが結成され、配列を公開する方針を固めたのは、1996年のこと、2001年に解読の概要版を発表したのち、今回解読完了を宣言したのである。
ただし今回の成果は、じつは配列を読み尽くしただけであって、遺伝子がもつ機能や遺伝子の指示でつくられるたんぱく質がどう協調して働くのか、病気は手短に言えば、たんぱく質の変調と考えられ、その構造や機能の解析は新しい医薬品の創製につながってくる。これから遺伝子の研究は、わたくしたちの暮らしにどう役立てられるか、これこそもっとも大事な目標であって、そんな成り行きをじっと見守って行きたい。
英語を学習するための強力なパートナー
「コーパス」解析とは
英語を学ぶには、「語句」の使い方をまずマスターすることが大切だが、従来その使い方はもっぱら経験によって教えられてきた。そこであまりに基礎的な単語については辞書の説明が不十分であったり、用例として少し変わった言い回しが採用されるなどしていた。
英語学習の強力なパートナーとして、新しい方法、「コーパス」が登場した。コーパスとはアメリカやイギリスで実際に使われている英文のテキストデータを収集した、膨大なデータベースのこと。これを活用することによって、語句の重要度を決定する方法や用例の選び方が、客観的に裏付けされ、「コーパス」で解析すると、その単語がどんな意味でどんな場合によく使われているか、またその単語の前後にはどのような語句が用いられるかが分かる。
NHK教育テレビに4月から登場した「100語でスタート英会話」(講師:投野由紀夫)は、このコーパスのデータベースを使った番組で、
毎日10分のレッスンで英会話力をブラッシュアップするポイントが盛り込まれ、 中学2年で習う会話レベルで無理なく上達するカリキュラムが組まれている。
一例を挙げて見よう。
■「have」 基本的な意味は「〜を持つ」
have + 名詞のトップ10は:
1:look 2:time 3:place 4:money 5:problem(s)
6:children 7:idea 8:day 9:job 10:chance
文例として:have a look have time to + 動詞
have a chance to + 動詞
have difficulty …ing
have a problem with …
■つぎは「go」 基本的な意味は「行く」
go to + 名詞のトップ10は:
1:bed 2:school 3:sleep 4:work 5:church
6:town 7:court 8:college 9:the hospital 10:a [the] doctor
文例として:I want to go to + a bookstore(場所)
go to bed / go to school / go to work
■つぎに「get」 基本的な意味は「〜を手に入れる」
get + 名詞のトップ10は:
1:money 2:job 3:time 4:car 5:work
6:number 7:book 8:chance 9:house 10:idea
文例として:How can I get + (もの)?
get money / get a job / get a chance
コーパス解析をベースにした「ウイズダム英和辞典」(三省堂)¥3100が発売された。

かしこい患者になろう
検査値に神経質にはならないで…
職場や地域の健康診断で、あなたの検査値が基準値を外れていると知らされると、よい気分ではいられない。医師が検査値について何らかの説明をしてくれる場合にはまだしも、判定表や「要精密検査」の通知を受けとると、神経質にならざるを得ない。
しかし基準値なるものについて考えてみよう。第一に基準値はもともと95%の健康人がもつ値なので、一項目について5%の健康人は外れる。10項目とも規準値の範囲に収まる人は60%しかいないことになるのだ。
最近の厚生労働省の発表によると、一千百万人あまりの検診で、規準値を外れた人は半数近くいたとのことだ。
第二に病気でなくても、検査値はかなり変動する。朝日新聞に編集委員の田辺功氏が書かれた記事によると、新年会の御馳走を食べたあと、コレステロール値が上がり、特にウニ、イクラなどの魚卵を沢山食べたあとは、2、3日後から2週間くらい高い値が出るという。暴飲、暴食は避けなければいけないが、しばらく御馳走を休み、次回の検査値を待ってという手もある。それでも決定的に手遅れになるということはない筈だ。
文字データを扱うときのヒント
「テキストファイル」を使おう
文字や文章を扱う「ワープロ」という機種は、その影が薄くなって、ショップの店頭から消されてしまった。
パソコンの機能がめっきり増え、絵や写真などのデータを取り扱うことが多くなって、従来の単機能の「ワープロ」では物足りなくなったからだろう。
しかし、何でもできるパソコンの制作で、文字入力と文章の作成、すなわちワープロ (Word Processing が短縮された日本語)のソフトを使う作業は欠かせない。
ワープロデータについてだが、よく知られているように、日本語のワープロソフト「一太郎」のデータをマイクロソフト社の「Word」(Windowsでひろく使われるソフト)で読むことはできない。ワープロソフトが異なると、データに互換性は無い。また厄介なことに、ソフトのバージョンが違っても、データを開けられないことがある。
ここで本題に入ることにしよう。文字データを誰かと交換するとき、一番確実なのは、「テキストデータ」だ。「テキスト」ファイルは、どのパソコンソフト上でも開けることができ、汎用性をもっている。
Microsoft「Word」を使うと、文章をモニター上に出力するとき、また、プリントするときにも、見栄えが良く、その他多くの機能も利用できる。しかし「Word」で保存したデータ、Word文書(*.doc)はほかのソフト上で読むことはできない。文字のやり取りに限れば、機能を絞ったテキストファイルを使うことがベストなのだ。「Word」を使っていても、保存するときに「テキスト」を選び、「テキストファイル」、テキスト.docにすると、読み書きは軽快になる。